患者さん・一般の皆さま
ポンペ病とは
生まれつき酸性α-グルコシダーゼと呼ばれる酵素を十分に持っていないために、グリコーゲンという物質がうまく分解されず、 からだの中に過剰にたまってしまうことにより様々な症状があらわれます。
ライソゾーム病の一種で、酸性マルターゼ欠損症、糖原病II型とも言われ、患者数が極めて少ない*希少疾患です。
- * 正確な発生頻度は分かっていませんが、世界で約5~10万に1人との報告があります1)
また、日本では約10~20万人に1人と推定されています1),2)
- 1) Kong W et al, Neuroscience, 2024, 63, 167-174 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39424261/
- 2) 小児慢性特定疾病情報センター、ポンぺ(Pompe)病 https://www.shouman.jp/disease/details/08_06_097/
症状があります*
早期発見と適切な治療が重要です
「指定難病」および
「小児慢性特定疾病(18歳未満)」
に指定され、
医療費助成制度等の
対象となっています
- *症状の現れ方やその程度・進行には個人差があります
原因
酸性α-グルコシダーゼと呼ばれる酵素を作る遺伝子の変化により起こります。
この酵素は糖のひとつであるグリコーゲンをブドウ糖に分解するために必要な酵素です。
酵素が不足してグリコーゲンを分解できなくなると、全身の細胞内、特に筋肉(骨格筋、心筋、平滑筋)、心臓、肝臓の細胞などにグリコーゲンがたまって、様々な症状があらわれます。
主な症状
人により症状やその程度が異なりますが、代表的な症状として下記のようなものがあります。
- 運動発達の遅れ
- 筋力の低下
- 呼吸のしにくさ
- 背骨の湾曲
- 腹痛や下痢などの消化管の症状
- 心臓の症状
「歩きづらい」、「疲れやすい」、「風邪をひきやすい・治りにくい」、「起床時の頭痛・日中の眠気」など、他にも様々な症状があります。
これらの症状は時間がたつにつれて悪化する場合があります。
症状の表れ方や進行には個人差があり、車いすや人工呼吸器が必要となる場合があります。
経過と分類
症状の現れ方やその程度・進行には個人差があります。発症する年齢によって以下のように分類されています。
小児型と成人型をあわせて「遅発型」と総称することがあります。
| 乳児型 | 新生児期から乳児期前半(6ヵ月未満)に発症し、症状が急速に進行します。生後数ヵ月で筋力が弱くなり、首がすわらない、寝返りができないなどの発達の遅れが見られます。また、心臓が大きくなる「心肥大」が特徴的です。心臓や筋肉への影響が強いため、早期に診断し治療をすることが重要です。 |
|---|---|
| 小児型 | 生後6~12ヵ月以降に発症し、筋力の低下がゆっくりと進行します。運動発達の遅れや呼吸が苦しいなどの症状が見られます。学校の体育の授業や遊びで同級生と同じ運動をすることが難しい場合があります。 |
| 成人型 | 成人期の幅広い年代に発症し、症状はゆっくり進行します。筋力が低下し、徐々に歩行が難しくなったり、呼吸がしづらくなったりします。心臓への影響は少ないことが多いですが、日常生活に支障をきたす場合があります。 |
診断
症状の確認に加えて、血液を採取してCK(筋肉に含まれる酵素)、AST、ALT、BNPなどの値を測定したり、乳児では心エコーや心電図、小児型・成人型では筋のCT検査や肺機能検査、睡眠時呼吸機能検査を行います。
確定診断のために行われる検査
酵素活性測定
血液中のリンパ球や皮膚組織から酸性α-グルコシダーゼの働きを測定する
遺伝子検査
酸性α-グルコシダーゼをつくる遺伝子に変化が起きているかを調べる
筋生検
筋組織のライソゾームにグリコーゲンが蓄積されているかどうかを調べる
症状が他の疾患と似ていて、診断までに時間がかかることがあります。
ポンぺ病の新生児マススクリーニング検査を実施している自治体や医療施設では、このスクリーニング検査が診断のきっかけとなる場合があります。
治療
「酵素補充療法」という、体内で不足している酵素を薬で補う治療法があります。この治療により、症状の進行を遅らせたり、改善したりすることが期待できます。
呼吸がしづらい場合には酸素マスクや人工呼吸器を使用してサポートを行います。
理学療法(リハビリ)を取り入れることで、関節の拘縮や変形を予防します。
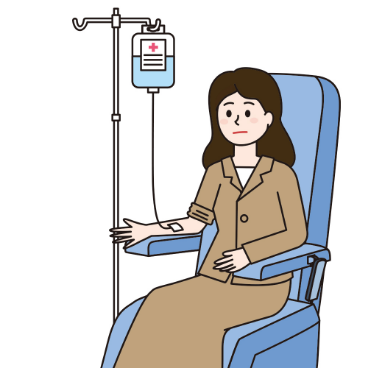

診療科
ポンぺ病の症状は全身に現れるため、以下のように複数の診療科が関わる可能性があります。
- 小児科
- 小児神経科
- 遺伝診療科
- 総合内科
- 循環器内科
- 呼吸器内科
- 神経内科
- リハビリテーション科
など
気になる症状がある場合には、かかりつけの小児科や内科の医師に相談してください。
必要に応じて詳しい検査を行ったり専門医や専門外来のある医療施設を紹介してくれます。
患者会・支援団体等
遺伝カウンセリングや難病支援相談センター、患者支援団体などの相談・支援先があります。
ポンぺ病に関する情報と資料
参考
- 難病情報センター ライソゾーム病(指定難病19)
https://www.nanbyou.or.jp/entry/4061(令和7年2月4日閲覧) - 小児慢性特定疾病情報センター ポンペ(Pompe)病
https://www.shouman.jp/disease/details/08_06_097/
(令和7年2月4日閲覧) - 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業)ライソゾーム病、ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを含む)における早期診断・早期治療を可能とする診療提供体制の確立に関する研究 ポンぺ病
http://www.japan-lsd-mhlw.jp/lsd_doctors_pompe.html
(令和7年2月4日閲覧) - 日本先天代謝異常学会編集 ポンぺ病診療ガイドライン2018 pompe2018.pdf
